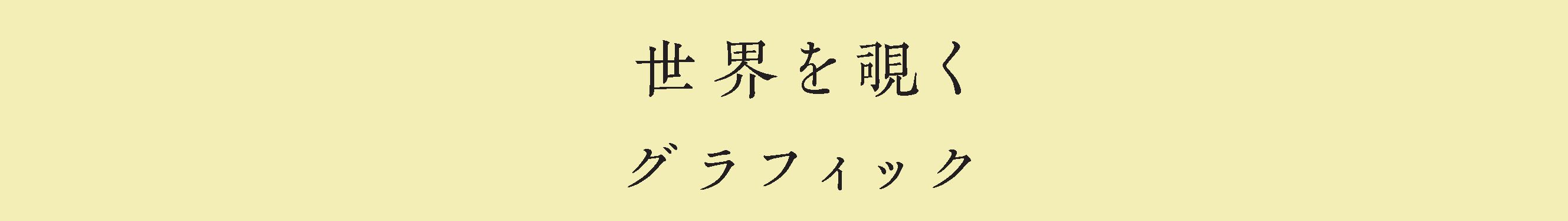『アイデア』No. 382「グラフィズム断章:もうひとつのデザイン史」に寄せて
『アイデア』382号への参加デザイナーからのコメント
2018年6月発売の『アイデア』382号刊行に寄せて,参加デザイナー各氏からいただいたコメントを掲載します。
「Room A:これまでのグラフィックデザインから考える13の断章」参加デザイナー
グラフィック・デザインの難しさ(おもしろさ)は誠実に向き合えば傑作を生み出せるとは限らないところだ。
簡単に言えば運みたいなものに近く,努力や鍛錬が無効な世界。にもかかわらず,みんながそれぞれの方法で誠実に向き合っている。
そんな姿を垣間見ることができて励みになった。
「Room C:来たるべきグラフィックデザインのための図書室」参加デザイナー
全ての行動がデザインとして反映されてしまうのではないか,という気持ちになるほどウェブへの接触時間が長い。いつでもロギングと,誤解のリスクがつきまとうからウェブは面白いのであるが,今でも自然な態度はどこであるだろうと模索している。今回のグラフィズム断章には選書という形で参加させていただいたが,参加された他の方々のセレクトを見て,そうした悩みが気恥ずかしくなるような豊穣さがあったように思って,少し嬉しくなった。だから同様の機会があったら,デザインの実装が(ニーズではなく,提案としての)新しい機会にどう向き合うのかについて,あえてもう少し踏み込んでみたい。デジタルに関しては,初代のApple Human Interface Guidelineには「アイコンをはじめとしたUI類はグラフィックデザイナーに託すことも検討するべき」とあった。今はUIデザイナーに描いてもらいましょう,になるのだろうか? アセットをどこかで拾ってきましょうとそこに書かれる世界はもう目と鼻の先まで迫っていて,個人的にはそれについてもう少し考えておきたい。デザインはオートマトンに翻弄されるのではなく,認識に翻弄されるのだから。
あの展覧会はモノである以上にコトだったのだなと今になって思う。参加者各自が切り取る「デザイン」という切り口。個から立ち上がるパーソナルなものだからこそ,個の内側で大切にしてきたコトを紐解く過程を含めて,その状況を目撃するというような「ゆらぎ」を感じる展覧会だった。それは,確固として確立した通史としての「デザイン史」とは全く異なる風景。パーソナルだからこそ,仕事として体得してきた問題意識と個の興味が,ある視座を獲得しそこに「生」のまま提示されているような。
「デザイン」という単語は,現状では意味が飽和し,マクロで捉えようとしてもつかみどころのないゴーストのような印象がある。その中でデザイナーの体験に基づいた個の歴史と,主語を極限まで小さくした「私」から語るミクロな「デザイン」。個の身体から導き出される具体性を持った視点。「私」から見た「世界」。雑多なカオスから受ける多様性の宇宙のようなもの。ミクロとマクロ,その視座の有機的な運動から得るバランス感覚こそが「デザイン」という総体なのかも,とも。
完成された「デザイン史」に対して,現在進行中のものを語るには,流動的・可変的・多動的な「ゆらぐ」ものとして,生のまま提示する「場」としての設えが必要なのだと思う。そのチャレンジャブルな試みは,「見逃してはいけない」と思わせる,一回性・事件性・演劇性を孕んだ形で,一端を可視化することに成功したのではないか。これはデザイン業界の事件だと感じ,見落としたくなくて毎週末トークに足を運んだ自分の行動も,この展示の性質に由来する。
大学で油画を学び,デザインを仕事と独学で学んできたものとしては,デザイン正史(デザイン正史というものがあるのなら。教科書的な)の外側にいると思っていたところ,外側にいることも「もうひとつのデザイン史」として独自に歩んでいけば良いのだなと。自分なりの「ミクロとマクロ」のバランスを探りながら歩んでいければと思う。
本展示を通して大きく感じたことは,
グラフィックデザイナーという職業に対しての向き合い方・姿勢に
人の数だけ違いがあるということを
再認識するきっかけの一つとなったと思えることです。
その人自身の考え方・散らばる情報への解釈の上に立ち,
仕事をつくっていくことが可能なのではないかという
可能性を感じられたこともありました。
グラフィックデザインにこれからがあるとして,
一つの中継地点のような展示だったのではないのかと思いました。
勇気を持って前に進めたらと思いました。
選書のパートに参加したので本について考えた。
本はそこに新しいことが書かれているものでもあるが,脚注に出典がずらっと載せられた効率のよいリンク集のようなものでもある。でもそのことは,注や索引のある本を読まなければ知らないことだし,僕のように大学で卒論を書かなかった人にとっては実際にそれを編むこともないものだ。
「グラフィズム断章」の展示の前後に,牧君(牧寿次郎)と話をした。なぜ「選書」は取り上げるものを本に限っているのか,「来たるべきグラフィックデザインのため」なら,ウェブサイトや展示に言及してもいいのでは,ということについて。デザイナーってそんなに本読んでるの?とは思っていたが,牧君に言われて確かに,そうかもね……?と思った。
しかしよく考えたらこの展示・特集自体が,本という形式を自明なものとして親しんだ人の考える企画だな~と思えてきた。つまり展示が,文献リスト付の一般的な本や論文のように作られているということ,そしてそれを今意義深いだけでなく何十年後でも追跡可能なものにしようとしていること。だからよりインフォーマルな言及・参照のしかたに親しんでいる人にとっては,本に限るというのは制限されているように感じるのかな~などと思った。
でも編集者やキュレーターのそういう意図に触れるのは,いつでも意義深い。自分の仕事もいつか記録され歴史の蓄積の一部になり(決して巨匠にならずとも,必ず未来のばるぼらさんのような人がディグってくれるだろうから……ていうかディグって……)誰かがまた言及する,ということを意識した仕事ができるから。
G8で行われた展覧会「グラフィズム断章」,その別の形としての『アイデア』382号を読む。私は「来たるべきグラフィックデザインのための図書室」のために5冊の本をあげた。自身が選んだ本も含む235冊を改めて眺め,それらが並ぶ図書室を想像してみるが,あまり楽しい気持ちにはならない。
その図書室に通い詰めて生まれるのは「非歴史的」ではないかもしれないが,やはり偏ったアーカイブを蓄積した「非人間化」されたデザイナーではないだろうかと思う。会場で47組すべての推薦文を読んだが,近田火日輝さんの70字には心打たれた。
デザイナーが社会にとって意義深い職種,あるいは人間である。という前提に苛立つ。私もそのことに無自覚ではなく,積極的に加担しているからなのだが,ただ苛立っているだけの自分に腹も立つ。腹が立ったら身体を動かし,苛立ったら本を読み,街に出る。だが,たまたますれ違う名も知らぬ人に話しかける術を,私たちは知らない。
この“個々”の時代に,「さあ,みんな!デザインについて,一度立ち止まって考えましょうよ。」と,投げかけられたような展示が「グラフィズム断章」でした。
「授業」のような展示からの,誌面化は「復習」のような作業。
歴史を紐解きながら,じっくり地質調査したG8での展示から,さらに深めた,『アイデア』No.382への誌面化。
そして,さらにこれから必要なのは,私たちが土壌を耕し,肥料も適宜まぜながら,花が咲くか,果実が実るかわからないけど,これからのデザインを育てていくこと。
これらを経て,またここからデザインの未来が見えてくるといいなと思います。
この社会の状況で,デザインを続けるのは,それなりに楽ではないと思いますが,誇りを持って,仕事をしていきたいものですね。
そして,このあとの世代にも,脈々と続いていきますように。
僕はカラスのデザインは文句なくすばらしいと思うんですが,それはデザイナーの仕事ではないし,人間が考えたデザイナーの哲学にそって作られたものでもありません。
ユリもすばらしいし,スズメもカバもすばらしいです。
だからまあ,デザイナーだろうがグラフィストだろうがどうでもいいんじゃないかというのが僕の正直な感想です。そんなところに自負のよりどころを持っているかぎり,デザイナーって進歩しないんじゃないでしょうか。
僕は「デザイン」と「デザイナリィ」を区別すべきだと思います。
後者はいま適当に作った言葉ですが,デザイナーのわざ,社会的いとなみ,まあだいたい商売のことです。タイポグラフィやベーカリィと同じです。
いっぽう前者はそういう人間の営為に先行して存在する,「ある物事のありようを,外界への応答として見ること」です。カラスの形のすごさと,ヘルベチカのカッコ良さを同列に論じたいわけです。
そういう「デザイナーに先行して存在する畏怖すべきデザイン」に,どうやったら肉薄できるか,というところに面白さはあるし,そこにしかないと思います。その面白さは,べつに問題解決には限らないし,社会のなかにあるわけでもない。無人島にいる人だってデザインの面白さを感じることは可能です。そして面白いことをするからおカネがもらえるわけです。
僕がいまのところ思っているのは,最適化と多様化がなぜか調和して両立しているとき,人間はそこにデザインを感じるということです。モズのようなシンプルさも,孔雀のような装飾性もデザインの一面で,かつそれは社会に先立って存在します。だから宮本武蔵のモズにも,伊藤若冲の孔雀にもデザインへの感動があると思います。
そういうデザインからさまざまなデザイナリィが分岐する。横尾忠則先生のデザイナリィもあれば,原研哉先生のデザイナリィもあります。デザインにはtheがつくかもしれないけど,デザイナリィはaの世界です。
で,モダンデザインと言っているものは,実はモダンデザイナリィです。「モダン(近代)」という外界に注目して,そこへの応答を重視するとこういう解もあるんじゃないのっていう方法論にすぎないんであって,モダンがモダンでなくなったらじゃあにこにこ笑ってよそに行こうかって話,行きつけのラーメン屋が定休日だったらきょうは牛丼食べてみようか,あるいは自炊,ぐらいの話で,そんなところに生死をかける必要はまったくないと思います。
そして同様に,グラフィズムという提案も結局デザイナリィの話なんじゃないかなーと思うわけです。
さて,さきほどデザインを「ある物事のありようを,外界への応答として見ること」と言ったわけですが,これをひとことで「ストーリー」という言葉にまとめたいと思います。万物にストーリーがある,ということがデザイナーを駆動するわけです。
StoryとHistoryは同根の言葉で,フランス語なんかでは単語が分かれてさえいないわけですが,だからモダンデザイン(デザイナリィ)のヒストリーは,ストーリーのひとつとして,ある物事のありようを規定しうると思います。でもそこに必然性なんてないし,ほかにたくさん魅力的なストーリーはあり,それはまったく同様にデザイナーを駆動します。
宗教もストーリーなら,ディープラーニングもストーリー,一本の漫画だってストーリーです。べつにそのなかでどれを選ぶべきかなんて問題を立てる必要はないし,複数をつまみ食いしながら面白いものを作るのが正しい楽しみ方だと思います。
この雑誌の名前が「デザイン」ではなくて「アイデア」であるのはとても良いことだと思います。そしてこの雑誌が漫画・アニメ・ライトノベル特集号をはじめ,「ところ変われば品変わる」博物学的な興味の号をいくつか作ってきたのは,そういう点で意義深いと思います。世の中にはいろんなストーリーがあるし,それでごはんも食べられるんだよってことです。
「グラフィズム断章」展の選書に挙げた『踊るミシン』『虫と歌』はいずれも著者自装の本です。選書依頼があったとき,身も蓋もない話ですがモダンデザインについてあまりにも不勉強なところから,自分の土俵である漫画に引きつけて選書したというのは事実です。とはいえ上記のような理屈を一応こねてあり,「ストーリーがデザイナーを駆動する」端的な例として挙げました。
そのへんの弁解を一度は選書コメントに書いたのですが,400字とのことでとても紙幅が合わず,もういいやと70字くらいにぶった切って提出しました。このたび2000字までという寛大なお申し出をいただいたので,酔っ払いのからみトークめいた散漫さですが,文章にしてみました。ご感想・ご叱正のだん,たぶん太刀打ちできないと思うのでどうぞそっと胸に秘めてください。
雑誌として出来上がった『アイデア』382号を手に取って,いささか複雑な気持ちになっている。
誤解のないように言っておくと,届けられた誌面デザインに不満があるわけでは,もちろんない。あの展示をたんに図録的なアーカイブとするのではなく(その機能も担保しながら),「雑」誌というメディアに定着させた結果としての誌面レイアウトは,間違いなく最良の答えのひとつだと思う。
ならばどうして複雑な心境なのかといえば,それはやはり展示と,こうして誌面として示された内容とのあいだを行き来して,突きつけられるものがあるからだ。
Room Aの展示デザイナーは各々が誌面レイアウトを担当している。各デザイナーによってレイアウトの方法は異なるのだが,批判を恐れずに言うのなら,不思議と似通った印象になっている感がぬぐえない。より正確に言えば,トーンとマナーが同じ,ということだろうか。展示でそれぞれが扱っているテーマがまったく違っただけに,平面のグラフィックとして定着された結果が同一の雰囲気を携えていることに驚きを覚えている。手法が拙いと言っているのではない。このレベルの人たちに,技量としての差があるとは思えないし,そういうことを指摘しているのではない。ただ,展示で示されていた明確な差異が,平面に落とし込まれたときに,図らずも消失してしまっている(平均化されてしまっている)のはなにによるものなのかと,考えてしまうのだ(ただし長嶋りかこと川名潤のページに関しては,その限りではない。前者は誌面化にあたりメッセージの伝達を第一に,非常に高水準で丁寧なレイアウトを実現しているし,後者は装丁を主戦場とするデザイナーらしく,ワンアイデアで強度のある表現を実装してくれた。また「いまデザイナーであることの意義」に明確に向きあうという姿勢においても,両者には共通するものがあるように思う)。
室賀清徳の「編集後記」と後藤哲也の「“日本のグラフィックデザイン”を更新する試みとしての展覧会」(以下「更新」)の射程の違いにも,戸惑いを覚えた。本展の実行委員である両名の,総括としてのテキストだが,「編集後記」が批評としてかなり突っ込んでいるのに対し(あのテキストを読んだあとでなにも考えずにSNSで自己宣伝できる厚顔無恥さを,自分はもちあわせていない),「更新」で吐露されたのは個人的・内的動機であって,展示の振り返りにまではいたっていない。「グラフィックデザインの死体をきちんとのばし,ひろげ,ならべる」ために企図した展示が,「つまるところ,我々がやりたかったことというのは,グラフィックデザイナーが集い,共に考える場をつくること,そのためのフォーマットだったと言える」ということなら,それはあまりに自己充足的に過ぎる。「更新」には,パッケージされた展覧会としてではなくスタディルーム形式の展示だったのことの意図や,こうした展示をつうじて社会との対話を繰り返すことでデザインを社会化し,共有可能な言語としていくことの重要性が記されているだけに,この文章が無意識的に孕むある種のムラ意識は,なおさら根が深いと思ってしまうのだ。断っておくが,後藤本人のことを否定・批判するつもりは毛頭ない。自分にも少なからずそうした意識があることは否定できない(帰属コミュニティへの信頼感)。だがその無意識に向きあうための契機として(も),本展があったのではないだろうか。
会期中の本展に足を運んだ何人かの友人から,「文化祭みたいだね」と言われた。完成された展示ではないことの意味(後藤が「更新」で示したことは,もちろん理解している)を自分なりに伝えたけれど,「内輪ノリ」の気分をどこか否定できない自分がいた。それはいま指摘したような無意識的な連帯感による部分もあるのだろうが,もっと言えば,歴史と権威のある『アイデア』という媒体に寄生しなければ,自分たちの仕事や存在の社会的な価値や意義をパブリッシュ=社会へ向けて発表することすらできない,われわれデザイナー自身のナイーブさに帰因しているように思えてならない。結局,ぼくらはいまだに「エンブレム騒動」が突きつけた課題に,なにひとつ答えられていない。
本展を経たところで,こうした状況が変わるわけではない。だが,今回デザイナーたちが主導して展示を実現しそれを誌面に結実させ,批評にさらされる地平を獲得できたことは,素直によろこばしいと思う。肝心なのはここからだ。きちんと絶望しながらもシニシズムに陥らず,いたずらに否定的な言説は斥けながら,けれど空気を読まず,誰に届かずとも,流れに棹さして声をあげつづけなければ,ほんとうになにも変わらない。そのための一里塚として本展があったのだと,いつの日か伝えられることを夢みているし,そのプロセスが共有可能なかたちで展開されることを願う。
今回、国外在住デザイナーとして参加した感想です。
まず一読者として、日本のグラフィックデザインの今の空気感を伝える充実した内容だと思いました。情報の量・質ともに普段ネットで得られるものとは桁違いでただただ圧倒されました。これだけの数の現役デザイナーが、自身の興味や問題意識を語る場を目にする機会は貴重です。個人的には、「デザインのモラル」に関する提議が、評論家ではなく当事者であるデザイナー自身から多くあげられたことが印象的でした。
一方で、自分がどこまでこの空気感を「読めて」いるのか、誌面を追いながらずっと不安でした。圧倒的な熱量は伝わってくるのですが、奥にある個々の動機や感情となると、東日本大震災やエンブレム問題のような出来事を身近に経験していないわたしには、表面的に理解することはできても、心の底から実感することは不可能なように思われたのです。
ヨーロッパの片隅で、移民として細々とフリーランスデザイナーを続けているわたしが日々抱えている問題は、この特集で紹介されているものとはまた少し違ったものです。それをどうやったら共有できるのか、そもそも共有する意味やメリットはあるのか、ずっと考えています。ぜひこのような企画を定期的に続けてください。考える糧になります。
どんな分野でも「黎明期」は面白いものだ。自分が子供の頃はまさにTVゲームの黎明期であったが,面白いのかつまらないのかもよく分からない玉石混交のゲームが大量に流通し,多くは忘れられつつも強く心に刻まれるような名作にもたくさん出会った。あのカオスな雰囲気は草分け時代の醍醐味であると思う。そして正直に告白すると,デザインに興味を持ち始めた10代後半,僕は「日本におけるグラフィックデザインの黎明期は数十年前に過ぎ去ってしまった」という勝手なイメージを持っていた。自分はデザインにこんなに興味を抱いているのに,どうしてもっと早く生まれなかったんだろう,という屈折した思いを抱えていたのだ。
ひるがえって,この展覧会で本を選定しているとき,「ひょっとしたら他の人とかぶってしまうのではないか」とひそかに心配していたのだが,まったくの杞憂であった。デザイナーたちの思考は,想像よりずっと大きな広がりを持っていて,周囲が見えていなかった自分がとても恥ずかしくなった反面,「ああ,自分は,好きなことを好きなように突き詰めていけば良いだけなのだな」と解放された気持ちにもなった。方向性は違えど,皆現代におけるグラフィックデザインの価値を自分なりに再解釈しようと思考を巡らせていることがよく伝わってきて,勇気づけられた。
いわゆる戦後の日本グラフィックデザイン史を,憧れと諦めをもって眺めていた10代の自分に伝えてあげたい。「黎明期が終わってるって解釈は一面的なのでは?」「20年後のデザインの世界,色々しんどいけど,まだまだ面白いと思います。」
各デザイナーのプロフィールはこちら